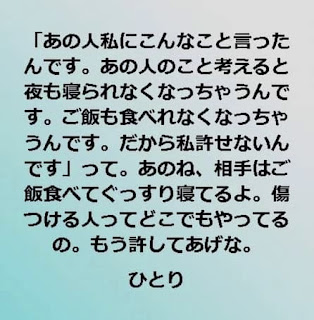2023・2・28・火曜日
極真空手浜松大蒲道場
押忍
#極真空手
#浜松市
#浜松
#東区
#大蒲町
2023年2月28日火曜日
2023年2月26日日曜日
極真会館 三重東道場 審査会
2023・2・26・日曜日
本日、三重東道場審査会に審査員として出席させて頂きました。
審査員として参加させて頂きながら、大変勉強もさせて頂き、また、最後には極真初段への登竜門 10人組手も執り行われ、大変な感動を頂きました、誠にありがとうございました!
押忍
#極真空手
#三重東
#審査会
#審査員
#10人組手
#十人組手
本日、三重東道場審査会に審査員として出席させて頂きました。
審査員として参加させて頂きながら、大変勉強もさせて頂き、また、最後には極真初段への登竜門 10人組手も執り行われ、大変な感動を頂きました、誠にありがとうございました!
押忍
#極真空手
#三重東
#審査会
#審査員
#10人組手
#十人組手
2023年2月25日土曜日
2023年2月24日金曜日
2023年2月23日木曜日
2023年2月21日火曜日
2023年2月20日月曜日
2023年2月19日日曜日
型・スパーリング会
2023・2・19・日曜日
極真空手 静岡西遠愛知東三河支部「型・スパーリング会」
朝9時〜昼12:00過ぎまでの3時間以上、、
改訂型とスパーリングのみ(ノーサポ顔面掌底有り、サポあり極真ルールまで)を延々と繰り返し稽古しました。
日曜午前中休日の貴重な3時間、とにかく、「愉しかった」この一言に付きました!^ ^
皆さん、本当にありがとうございました!
押忍
#極真空手
#型
#スパーリング
#組手
#手合わせ
極真空手 静岡西遠愛知東三河支部「型・スパーリング会」
朝9時〜昼12:00過ぎまでの3時間以上、、
改訂型とスパーリングのみ(ノーサポ顔面掌底有り、サポあり極真ルールまで)を延々と繰り返し稽古しました。
日曜午前中休日の貴重な3時間、とにかく、「愉しかった」この一言に付きました!^ ^
皆さん、本当にありがとうございました!
押忍
#極真空手
#型
#スパーリング
#組手
#手合わせ
2023年2月18日土曜日
2023年2月17日金曜日
2023年2月16日木曜日
【「心の空間」の法則】
斎藤一人さんの心に響く言葉より…
この前、ある女の子から、こんな質問が来たの。
「付き合っている彼氏と別れることになってしまいました。
『この人は運命の人だ!』と思っているほど大好きだったのに、縁が切れてしまうのは、どうしてでしょうか?」
縁が切れる原因って、いろいろあるよね。
人によって違うんだけど、ほとんどの場合は、「相手の"心の空間"をおかしたこと」なんだよな。
この世には、「"心の空間"の法則」っていうものがあるんだよ。
人には、自分に必要な"心の空間"っていうものがあるんだよね。
"心の空間"っていうのは、「自由に、のびのび動ける場所」っていうのかな。
"心の空間"がたくさん必要な人と、少しでも大丈夫な人と差はあるかもしれないけれど、必ず「必要な"心の空間"」っていうのがあるの。
その"心の空間"を、人からおかされたらイヤだよね。
たとえ、付き合っている相手だったり、結婚相手だとしても、自分の"心の空間" をおかされると、ものすごくイヤなんだよな。
たとえば、奥さんが「韓流ドラマ」が好きで、韓国の俳優をおっかけているとするよね。
それで、その奥さんのダンナも「韓流ドラマ」が好きだったら、夫婦で一緒に楽しめて、「楽しい"心の空間"」が大きくなります。
でも、ダンナは「韓流ドラマ」に興味がなくても、それはそれでいいんだよ。
奥さんに「おまえは、韓流ドラマ好きだもんな。十分楽しみなよ」とか言っていればいいんだよな。
それは、相手の"心の空間"を認めてあげたことになるんだよ。
だけど、「韓流ドラマなんてくだらないもの、見るのやめろ!」って言うのは、奥さんの"心の空間"に踏み込んで、相手の"心の空間"を減らそうとしていることになる。
こういうことをされると、奥さんは、ダンナのことがつくづくイヤになるんだよね。
結婚してからも、付き合っているときでも、相手が好きでたまらないときは、お互い相手の"心の空間"に入り込んでも、文句を言わない時期があるんだよ。
だけど、 お互いがもともと他人だから、相手とは違う"心の空間"があってあたりまえなんだよな。
「この人は、このくらいの空間だから」って、認めてくれる人とは、長く一緒にいられるんだよ。
だって、「"心の空間"を認めてくれる人」は、自分の"心の空間"の中にいてもいいもんな。
相手の"心の空間"を認めなかったり、減らそうとする人がそばにいることが耐えられないんだよ。
もしかすると、この質問をくれた女の子は、相手の"心の空間"の中に入り込もうとするクセがあるのかもしれないね。
愛があるから、相手の"心の空間"にズカズカ入っていいんじゃないんだよ。
愛があるから、相手の"心の空間"を大事にして、守ってやらなきゃいけないんだよな。
『おもしろすぎる成功法則』サンマーク出版
https://amzn.to/3XCTMXv
この"心の空間"の話は、なにも恋人同士の話だけではなく、夫婦や友人、同僚や仲間などにも言えることだ。
自分の心の中に土足で入り込まれて気分がいい人はいない。
話したくないことを根掘り葉掘り聞かれることほど嫌なことはない。
大敬先生は「人間の交わり」についてこう語っている。
『私たちの交わりは、清交、淡交でありたいなあと思っています。
清らかで、さわやかで、あまり人の仕事や家庭や、心の内側にまでズカズカ立ち入らない、淡い、まみずのような交わりであればと思っています。
そのまみずの中に、無量の味わいを感じとれる人になってほしいと思っています。
自分が正義と信じることを、その人が迷惑がっているのにも気づかずべつの相手に語ったり、どんどん文章を送りつけたりするのではなく、相手のわずかの表情の変化や動作や言葉から、その人の内心の思いを読み取れるほどの思いやりの繊細さを持つ人になってほしいと思います。
何事も行きすぎないよう、やりすぎないよう、すこし物足りないほどでとどめておくのが、万事における秘訣です。』(お日さまの教え 大敬先生<しあわせ通信>第四集/本心庵)
「君子の交わりは淡きこと水のごとし」とは、荘子の言葉。
その後に続く言葉が、「小人の交わりは甘きこと醴(れい)の如し」
あまり人のことには深入りせず、水のようにあっさりと付き合うことが、良い人間関係を長く続かせるコツ。
「醴」とは甘酒のように甘くてベタベタしていることを言うが、つまらない人間の交友関係は、ベタベタしていて、一時は深い交際のように見えても、それは長続きしない。
長く続く交わりには、余韻がある。
淡交と清交を目指し…
「心の空間」の法則を大事にする人でありたい。
■メルマガの登録と解除はこちらから
http://hitonokokoro.com/
■「人の心に灯をともす」のfacebookページです♪
http://www.facebook.com/hitonokokoro
■【人の心に灯をともす】のブログはこちら
http://ameblo.jp/hiroo117/
■Twitterはこちらから
https://twitter.com/hiroo117
シェアさせて頂きました。
斎藤一人さんの心に響く言葉より…
この前、ある女の子から、こんな質問が来たの。
「付き合っている彼氏と別れることになってしまいました。
『この人は運命の人だ!』と思っているほど大好きだったのに、縁が切れてしまうのは、どうしてでしょうか?」
縁が切れる原因って、いろいろあるよね。
人によって違うんだけど、ほとんどの場合は、「相手の"心の空間"をおかしたこと」なんだよな。
この世には、「"心の空間"の法則」っていうものがあるんだよ。
人には、自分に必要な"心の空間"っていうものがあるんだよね。
"心の空間"っていうのは、「自由に、のびのび動ける場所」っていうのかな。
"心の空間"がたくさん必要な人と、少しでも大丈夫な人と差はあるかもしれないけれど、必ず「必要な"心の空間"」っていうのがあるの。
その"心の空間"を、人からおかされたらイヤだよね。
たとえ、付き合っている相手だったり、結婚相手だとしても、自分の"心の空間" をおかされると、ものすごくイヤなんだよな。
たとえば、奥さんが「韓流ドラマ」が好きで、韓国の俳優をおっかけているとするよね。
それで、その奥さんのダンナも「韓流ドラマ」が好きだったら、夫婦で一緒に楽しめて、「楽しい"心の空間"」が大きくなります。
でも、ダンナは「韓流ドラマ」に興味がなくても、それはそれでいいんだよ。
奥さんに「おまえは、韓流ドラマ好きだもんな。十分楽しみなよ」とか言っていればいいんだよな。
それは、相手の"心の空間"を認めてあげたことになるんだよ。
だけど、「韓流ドラマなんてくだらないもの、見るのやめろ!」って言うのは、奥さんの"心の空間"に踏み込んで、相手の"心の空間"を減らそうとしていることになる。
こういうことをされると、奥さんは、ダンナのことがつくづくイヤになるんだよね。
結婚してからも、付き合っているときでも、相手が好きでたまらないときは、お互い相手の"心の空間"に入り込んでも、文句を言わない時期があるんだよ。
だけど、 お互いがもともと他人だから、相手とは違う"心の空間"があってあたりまえなんだよな。
「この人は、このくらいの空間だから」って、認めてくれる人とは、長く一緒にいられるんだよ。
だって、「"心の空間"を認めてくれる人」は、自分の"心の空間"の中にいてもいいもんな。
相手の"心の空間"を認めなかったり、減らそうとする人がそばにいることが耐えられないんだよ。
もしかすると、この質問をくれた女の子は、相手の"心の空間"の中に入り込もうとするクセがあるのかもしれないね。
愛があるから、相手の"心の空間"にズカズカ入っていいんじゃないんだよ。
愛があるから、相手の"心の空間"を大事にして、守ってやらなきゃいけないんだよな。
『おもしろすぎる成功法則』サンマーク出版
https://amzn.to/3XCTMXv
この"心の空間"の話は、なにも恋人同士の話だけではなく、夫婦や友人、同僚や仲間などにも言えることだ。
自分の心の中に土足で入り込まれて気分がいい人はいない。
話したくないことを根掘り葉掘り聞かれることほど嫌なことはない。
大敬先生は「人間の交わり」についてこう語っている。
『私たちの交わりは、清交、淡交でありたいなあと思っています。
清らかで、さわやかで、あまり人の仕事や家庭や、心の内側にまでズカズカ立ち入らない、淡い、まみずのような交わりであればと思っています。
そのまみずの中に、無量の味わいを感じとれる人になってほしいと思っています。
自分が正義と信じることを、その人が迷惑がっているのにも気づかずべつの相手に語ったり、どんどん文章を送りつけたりするのではなく、相手のわずかの表情の変化や動作や言葉から、その人の内心の思いを読み取れるほどの思いやりの繊細さを持つ人になってほしいと思います。
何事も行きすぎないよう、やりすぎないよう、すこし物足りないほどでとどめておくのが、万事における秘訣です。』(お日さまの教え 大敬先生<しあわせ通信>第四集/本心庵)
「君子の交わりは淡きこと水のごとし」とは、荘子の言葉。
その後に続く言葉が、「小人の交わりは甘きこと醴(れい)の如し」
あまり人のことには深入りせず、水のようにあっさりと付き合うことが、良い人間関係を長く続かせるコツ。
「醴」とは甘酒のように甘くてベタベタしていることを言うが、つまらない人間の交友関係は、ベタベタしていて、一時は深い交際のように見えても、それは長続きしない。
長く続く交わりには、余韻がある。
淡交と清交を目指し…
「心の空間」の法則を大事にする人でありたい。
■メルマガの登録と解除はこちらから
http://hitonokokoro.com/
■「人の心に灯をともす」のfacebookページです♪
http://www.facebook.com/hitonokokoro
■【人の心に灯をともす】のブログはこちら
http://ameblo.jp/hiroo117/
■Twitterはこちらから
https://twitter.com/hiroo117
シェアさせて頂きました。
2023年2月15日水曜日
2023年2月14日火曜日
2023年2月13日月曜日
【人は何歳になってもほめられたい】
小林正観さんの心に響く言葉より…
ある日突然、幼い子どもは何を「生きがい」にして生きているのだろうか、という疑問が私の中にわきました(幼い子とは小学生以下、くらいで考えてください)。
そう考えていたら、私なりの推論が浮かびました。
子どもは、もしかしたら「ほめられたくて」生きているのではないか、と。
「生きがい」が大げさすぎるなら、「何かをするための元気、エネルギー。その源」 と言いかえてもいいかもしれません。
幼い子どもは、「誰かにほめられたくて」生きているのではないでしょうか。
その「誰か」とは、その子によっては親だったり、おじいちゃん・おばあちゃんであったり、学校の先生であったり、あるいは塾の先生であるのでしょう。
基本的には信頼関係にある人です。
そういう人たちから「すごい」「よくやったね」と言われると、子どもは本当にうれしそうな顔をします。
そしてさらにやる気になる。
ほめるとどんどんやっていく。
やればやるほど、すごい才能と集中力を示す。
子どもは「ほめられたくて」「ほめられたくて」仕方がないみたいです。
ひるがえって考えます。
では、中学生や高校生 は....。
自分自身の興味や方向性が出てはくるものの、陸上競技をやるにしても絵画をやるにしても、誰もほめてくれなければたぶん早い段階で諦めてしまうことでしょう。
道を選んだのは本人でも、それを続けるエネルギーは、まわりの人の反応によるように思います。
青春期には、「ほめられたい人」(相手)が異性になる。
ある人と恋愛をする、ということは、その「特別な人」「特定の人」から「ほめられたい」ということなのかもしれません。
そういう人を確保することが「恋愛」というものの本質だとしたら......。
結婚し、家庭を持っても、妻はいつも夫にほめられたいと思い、夫も妻にほめられたいと思っているはずです。
そういう人を選んで結婚したのですから。
妻は「料理がおいしい」と言われれば結婚して何年たっていてもうれしいし、夫も「日曜大工がこんなに上手だとは思わなかった」と言われれば、どんどんつくってしまおうと思うでしょう。
「恋愛」や「結婚」の本質が、「好き」という概念よりも「この人からほめられたい」という概念に近いものであることに気づけば、結婚生活の中で何を続けていくべきかがわかります。
「好き」「愛してる」と言い続けることも素敵ですが、それが言いにくい日本の夫婦の場合は、「ほめる」ということで、互いを選んだことの本質をずっと確認し続け、維持できるような気がします。
「仕事の場でも、人はやはり「ほめられたい」のではないでしょうか。
私なども単純ですから、編集部から「よい原稿でした」などとほめられると、「次にはもっと『すごい』と言われたい」と思い、さらに元気とやる気が出て、調べものにも熱が入ります。
仕事場で、「この上司からほめられたい」と思う部下がいてくれたら、その上司 はそれだけで大きな幸せを得ているように思います。
多くの部下からそう思われる人だったら、部下を一度も叱りつけることなしに、相当な業績を残すことでしょう。
個人的なつき合いや人間関係でも、どんな人も常にほめられたいのだ、ということをわかって接したら、ずいぶん違うものになりそうです。
「今日の服はよく似合って素敵」とか「ネクタイがいい趣味」とか「歩き方がはつらつとしている」とか「今日は楽しそう」とか、本当にそう思ったことは遠慮なく口にしてほめるというのはどうでしょう。
人は、何歳になっても、どんな立場でも、きっと誰かにほめられたくて生きているのです。
大人の場合は「ほめる」という表現より「評価する」「認める」という言葉のほうが適切な気はしますが、根源的には同じものでしょう。
ただし、本当はそう思っていないのにお世辞でほめるのは逆効果。
言葉には「本当にそう思っている」場合にはエネルギーが必ず宿りますが、そうでなければ何のエネルギーもなく、むなしく響くだけだからです。
結局、人間関係には「この人にほめられたい」という人になれるかどうか、ということも大きく関わってくるという気がします。
『小林正観さんの 人生のシナリオを輝かせる言葉』主婦の友社
https://amzn.to/3LmsOi2
精神科医の名越康文氏は『「ほめること」と「驚く力」』についてこう語っている。(驚く力ーーさえない毎日から抜け出す64のヒント/夜間飛行)より
『例えばよく「ほめて伸ばす教育」ということが言われます。
でも、「ほめてあげる」という姿勢には、「ほめる人」の感動が感じられません。
上から目線で、心が動かされる感じがありませんよね。
一方、本当に上手に人をほめる人というのは、必ず非常に豊かな「驚く力」を持っています。
というのも、ほめる人が驚いているかどうかは、子供や生徒など、教えられる立場の人に必ず伝わっているからです。
そして、ほめる側の心に「驚き」が伴ったときの「ほめ」には、そうでないときの何倍もの力が宿る。
つまり、「驚き」には、人を導く力があるんです。
子供や生徒が何かをできるようになったときに、「え!こんなことができるのか!」と素直に驚くということ。
子供や生徒の中に、自分たちが想像もしなかった何かの存在を認め、それを自分の中に取り入れて「すごい!こんな可能性もあったのか!」と驚くということ。
そういう「驚く力」にあふれた人の「ほめ」には、人を動かす力があります。』
『人は賞賛を渇望する動物である』(田中真澄)
という言葉がある。
人は、誰かにほめられたくて仕方のない生き物なのだ。
それは、別の言葉でいうと、「認めてもらいたい」「評価してもらいたい」「共感して欲しい」「肯定して欲しい」ということでもある。
「人は、何歳になっても、どんな立場でも、きっと誰かにほめられたくてウズウズして生きている」
「ほめる力」と「驚く力」を存分に使える人でありたい。
■メルマガの登録と解除はこちらから
http://hitonokokoro.com/
■「人の心に灯をともす」のfacebookページです♪
http://www.facebook.com/hitonokokoro
小林正観さんの心に響く言葉より…
ある日突然、幼い子どもは何を「生きがい」にして生きているのだろうか、という疑問が私の中にわきました(幼い子とは小学生以下、くらいで考えてください)。
そう考えていたら、私なりの推論が浮かびました。
子どもは、もしかしたら「ほめられたくて」生きているのではないか、と。
「生きがい」が大げさすぎるなら、「何かをするための元気、エネルギー。その源」 と言いかえてもいいかもしれません。
幼い子どもは、「誰かにほめられたくて」生きているのではないでしょうか。
その「誰か」とは、その子によっては親だったり、おじいちゃん・おばあちゃんであったり、学校の先生であったり、あるいは塾の先生であるのでしょう。
基本的には信頼関係にある人です。
そういう人たちから「すごい」「よくやったね」と言われると、子どもは本当にうれしそうな顔をします。
そしてさらにやる気になる。
ほめるとどんどんやっていく。
やればやるほど、すごい才能と集中力を示す。
子どもは「ほめられたくて」「ほめられたくて」仕方がないみたいです。
ひるがえって考えます。
では、中学生や高校生 は....。
自分自身の興味や方向性が出てはくるものの、陸上競技をやるにしても絵画をやるにしても、誰もほめてくれなければたぶん早い段階で諦めてしまうことでしょう。
道を選んだのは本人でも、それを続けるエネルギーは、まわりの人の反応によるように思います。
青春期には、「ほめられたい人」(相手)が異性になる。
ある人と恋愛をする、ということは、その「特別な人」「特定の人」から「ほめられたい」ということなのかもしれません。
そういう人を確保することが「恋愛」というものの本質だとしたら......。
結婚し、家庭を持っても、妻はいつも夫にほめられたいと思い、夫も妻にほめられたいと思っているはずです。
そういう人を選んで結婚したのですから。
妻は「料理がおいしい」と言われれば結婚して何年たっていてもうれしいし、夫も「日曜大工がこんなに上手だとは思わなかった」と言われれば、どんどんつくってしまおうと思うでしょう。
「恋愛」や「結婚」の本質が、「好き」という概念よりも「この人からほめられたい」という概念に近いものであることに気づけば、結婚生活の中で何を続けていくべきかがわかります。
「好き」「愛してる」と言い続けることも素敵ですが、それが言いにくい日本の夫婦の場合は、「ほめる」ということで、互いを選んだことの本質をずっと確認し続け、維持できるような気がします。
「仕事の場でも、人はやはり「ほめられたい」のではないでしょうか。
私なども単純ですから、編集部から「よい原稿でした」などとほめられると、「次にはもっと『すごい』と言われたい」と思い、さらに元気とやる気が出て、調べものにも熱が入ります。
仕事場で、「この上司からほめられたい」と思う部下がいてくれたら、その上司 はそれだけで大きな幸せを得ているように思います。
多くの部下からそう思われる人だったら、部下を一度も叱りつけることなしに、相当な業績を残すことでしょう。
個人的なつき合いや人間関係でも、どんな人も常にほめられたいのだ、ということをわかって接したら、ずいぶん違うものになりそうです。
「今日の服はよく似合って素敵」とか「ネクタイがいい趣味」とか「歩き方がはつらつとしている」とか「今日は楽しそう」とか、本当にそう思ったことは遠慮なく口にしてほめるというのはどうでしょう。
人は、何歳になっても、どんな立場でも、きっと誰かにほめられたくて生きているのです。
大人の場合は「ほめる」という表現より「評価する」「認める」という言葉のほうが適切な気はしますが、根源的には同じものでしょう。
ただし、本当はそう思っていないのにお世辞でほめるのは逆効果。
言葉には「本当にそう思っている」場合にはエネルギーが必ず宿りますが、そうでなければ何のエネルギーもなく、むなしく響くだけだからです。
結局、人間関係には「この人にほめられたい」という人になれるかどうか、ということも大きく関わってくるという気がします。
『小林正観さんの 人生のシナリオを輝かせる言葉』主婦の友社
https://amzn.to/3LmsOi2
精神科医の名越康文氏は『「ほめること」と「驚く力」』についてこう語っている。(驚く力ーーさえない毎日から抜け出す64のヒント/夜間飛行)より
『例えばよく「ほめて伸ばす教育」ということが言われます。
でも、「ほめてあげる」という姿勢には、「ほめる人」の感動が感じられません。
上から目線で、心が動かされる感じがありませんよね。
一方、本当に上手に人をほめる人というのは、必ず非常に豊かな「驚く力」を持っています。
というのも、ほめる人が驚いているかどうかは、子供や生徒など、教えられる立場の人に必ず伝わっているからです。
そして、ほめる側の心に「驚き」が伴ったときの「ほめ」には、そうでないときの何倍もの力が宿る。
つまり、「驚き」には、人を導く力があるんです。
子供や生徒が何かをできるようになったときに、「え!こんなことができるのか!」と素直に驚くということ。
子供や生徒の中に、自分たちが想像もしなかった何かの存在を認め、それを自分の中に取り入れて「すごい!こんな可能性もあったのか!」と驚くということ。
そういう「驚く力」にあふれた人の「ほめ」には、人を動かす力があります。』
『人は賞賛を渇望する動物である』(田中真澄)
という言葉がある。
人は、誰かにほめられたくて仕方のない生き物なのだ。
それは、別の言葉でいうと、「認めてもらいたい」「評価してもらいたい」「共感して欲しい」「肯定して欲しい」ということでもある。
「人は、何歳になっても、どんな立場でも、きっと誰かにほめられたくてウズウズして生きている」
「ほめる力」と「驚く力」を存分に使える人でありたい。
■メルマガの登録と解除はこちらから
http://hitonokokoro.com/
■「人の心に灯をともす」のfacebookページです♪
http://www.facebook.com/hitonokokoro
教育
教育とは、
流れる水に文字を書くような
はかない仕事なのです。
しかし、それをあたかも
岩壁にのみで
刻みつけるほどの真剣さで
取り組まねばならないのです
━━━━━━━━━━
森信三(国民教育の師父)
『致知』2023年3月号特集「一心万変に応ず」より
━━━━━━━━━━
流れる水に文字を書くような
はかない仕事なのです。
しかし、それをあたかも
岩壁にのみで
刻みつけるほどの真剣さで
取り組まねばならないのです
━━━━━━━━━━
森信三(国民教育の師父)
『致知』2023年3月号特集「一心万変に応ず」より
━━━━━━━━━━
シェアさせて頂きました。
押忍!
2023年2月12日日曜日
自力の後に他力あり
浜松住まいEXPO はじめてのお稽古体験
おかげさまをもちまして体験50人以上の大盛況にて終了させて頂く事が出来ました。
「自力の後に他力あり」
やはり、時代は風の時代、競争よりも協力(助け合い)を痛感した一日となりました。
本日は誠にありがとうございました!
押忍
#住まいEXPO
#SBSプロモーション
#2023
#静岡新聞社
#静岡放送
#静岡新聞
#SBS
#静岡県
#浜松市
#極真空手
おかげさまをもちまして体験50人以上の大盛況にて終了させて頂く事が出来ました。
「自力の後に他力あり」
やはり、時代は風の時代、競争よりも協力(助け合い)を痛感した一日となりました。
本日は誠にありがとうございました!
押忍
#住まいEXPO
#SBSプロモーション
#2023
#静岡新聞社
#静岡放送
#静岡新聞
#SBS
#静岡県
#浜松市
#極真空手
2023浜松住まいEXPO
本日(2月12日日曜日)、10:00〜 サーラ(浜北)グリーンアリーナにて、
「浜松住まいEXPO はじめてのおけいこ体験」ブースを一区画任されております。
お近くにお住まいの方、是非、顔を見に来て頂けたら嬉しいです!
押忍^ ^
#住まいEXPO
#SBSプロモーション
#2023
#静岡新聞社
#静岡放送
#静岡新聞
#SBS
#静岡県
#浜松市
#極真空手
本日(2月12日日曜日)、10:00〜 サーラ(浜北)グリーンアリーナにて、
「浜松住まいEXPO はじめてのおけいこ体験」ブースを一区画任されております。
お近くにお住まいの方、是非、顔を見に来て頂けたら嬉しいです!
押忍^ ^
#住まいEXPO
#SBSプロモーション
#2023
#静岡新聞社
#静岡放送
#静岡新聞
#SBS
#静岡県
#浜松市
#極真空手
2023年2月11日土曜日
2023年2月10日金曜日
【「素朴愚拙」の魅力】
行徳哲男師の心に響く言葉より…
私は、人間の特に男の魅力というのは「素」「朴」「愚」「拙」の四つの言葉で表わすことができると思うんです。
「素」のよさは何も身につけていないことです。
カーライルが『衣装哲学』という本で述べていますが、いまの人間はいろいろと着込みすぎですよ。
枝葉をつけすぎている。
枝葉をつけた木は見栄えはいいけれど、滋養は枝や葉が吸ってしまい、幹や根が弱ってしまいます。
逆に枯れ木は見栄えはしませんが、力強さを持っている。
これが「素」の魅力ですよね。
「朴」とは泥臭さのことでしょう。
泥臭さがなければ本当の指導者にはなれないし、時代の救世主にはなれないんですよ。
作家の柴田錬三郎さんがシベリアに抑留されていたときに、極寒の中でしばしば靴下を盗まれたそうです。
そういう盗人はインテリや育ちのいい人間であったと書いています。
それに対して「俺の靴下を履けよ」と情けを示してくれたのは魚屋のおやじさんやヤクザ者だったそうです。
そういう限界状況で情を示せる人間というのは、どこか朴訥な田舎っぽいところがあったというんですね。
こういう朴訥(ぼくとつ)さをいまの指導者たちは失っています。
同時に「愚」がなさすぎる。
「大賢は大愚を見せるにあり」と言いますが、 大きな賢さというものは大きな馬鹿を見せることです。
「愚」の魅力とは阿呆になれる、馬鹿になれること。
そういう人物のもとには、「この人のために」 とたくさんの人が集まってくる。
それが本当の利口というものでしょう。
そういう「ど阿呆」が日本にはいなくなりましたね。
吉田松陰が一番好きだった言葉にこうあります。
「狂愚まことに愛すべし、才良まことに虞(おそ)るべし」
頭がいいだけの人間は恐ろしいですよ。
また、松陰はこうも言っています。
「狂は常に進取に鋭く、愚は常に避趨(ひすう)に疎(うと)し。才は機変の士多く、良は郷原(きょうげん)の徒多し」
愚の人は計算しません。
要領が悪い。
だからこそ、新しいことに挑(いど)めるわけでしょう。
でも、才良の士は郷原(きょうげん)の輩になってしまう。
すなわち、うわべだけ取り繕って人にこびたり、人を陥れたり、人を利用したりする。
いまはそんな人間が多すぎます。
馬鹿力と言いますが、馬鹿こそ力なんですよ。
最後の「拙」は下手くそのことです。
下手くそな人間は魅力的ですよ。
いまは上手に生きようとする人間、要領のいい人間があまりに多い。
『いまこそ、感性は力』致知出版社
https://amzn.to/3wAopSC
「気に入らぬ 風もあろうに 柳かな」
という江戸時代の臨済宗の僧侶、仙崖(せんがい)和尚の歌がある。
世の中には理不尽なことが多くある。
批判や、揶揄(やゆ)、嘲笑という風。
ときには大風が吹くときもある。
気に入らぬことも多いが、柳に風と受け流す。
受け流すことができる人は…
「素朴愚拙」の人だ。
また、「素朴愚拙」の人は、「深沈厚重(しんちんこうじゅう)」の人でもある。
中国明代の儒学者である呂新吾(ろしんご)が 名著『呻吟語』で「人物」について語っている。
深沈厚重(しんちんこうじゅう) 是第一等素質
磊落豪遊(らいらくごうゆう) 是第二等素質
聡明才弁(そうめいさいべん) 是第三等素質
第一等の人物は、深沈厚重の人で、どっしりと落ち着いて深みのある人物。
細事にこだわらない豪放な人物は第二等。
頭が切れて弁の立つ人物は第三等である。
「深沈厚重」であり…
「素朴愚拙」の人を目指したい。
■メルマガの登録と解除はこちらから
http://hitonokokoro.com/
■「人の心に灯をともす」のfacebookページです♪
http://www.facebook.com/hitonokokoro
■【人の心に灯をともす】のブログはこちら
http://ameblo.jp/hiroo117/
■Twitterはこちらから
https://twitter.com/hiroo117
シェアさせて頂きました。
押忍
行徳哲男師の心に響く言葉より…
私は、人間の特に男の魅力というのは「素」「朴」「愚」「拙」の四つの言葉で表わすことができると思うんです。
「素」のよさは何も身につけていないことです。
カーライルが『衣装哲学』という本で述べていますが、いまの人間はいろいろと着込みすぎですよ。
枝葉をつけすぎている。
枝葉をつけた木は見栄えはいいけれど、滋養は枝や葉が吸ってしまい、幹や根が弱ってしまいます。
逆に枯れ木は見栄えはしませんが、力強さを持っている。
これが「素」の魅力ですよね。
「朴」とは泥臭さのことでしょう。
泥臭さがなければ本当の指導者にはなれないし、時代の救世主にはなれないんですよ。
作家の柴田錬三郎さんがシベリアに抑留されていたときに、極寒の中でしばしば靴下を盗まれたそうです。
そういう盗人はインテリや育ちのいい人間であったと書いています。
それに対して「俺の靴下を履けよ」と情けを示してくれたのは魚屋のおやじさんやヤクザ者だったそうです。
そういう限界状況で情を示せる人間というのは、どこか朴訥な田舎っぽいところがあったというんですね。
こういう朴訥(ぼくとつ)さをいまの指導者たちは失っています。
同時に「愚」がなさすぎる。
「大賢は大愚を見せるにあり」と言いますが、 大きな賢さというものは大きな馬鹿を見せることです。
「愚」の魅力とは阿呆になれる、馬鹿になれること。
そういう人物のもとには、「この人のために」 とたくさんの人が集まってくる。
それが本当の利口というものでしょう。
そういう「ど阿呆」が日本にはいなくなりましたね。
吉田松陰が一番好きだった言葉にこうあります。
「狂愚まことに愛すべし、才良まことに虞(おそ)るべし」
頭がいいだけの人間は恐ろしいですよ。
また、松陰はこうも言っています。
「狂は常に進取に鋭く、愚は常に避趨(ひすう)に疎(うと)し。才は機変の士多く、良は郷原(きょうげん)の徒多し」
愚の人は計算しません。
要領が悪い。
だからこそ、新しいことに挑(いど)めるわけでしょう。
でも、才良の士は郷原(きょうげん)の輩になってしまう。
すなわち、うわべだけ取り繕って人にこびたり、人を陥れたり、人を利用したりする。
いまはそんな人間が多すぎます。
馬鹿力と言いますが、馬鹿こそ力なんですよ。
最後の「拙」は下手くそのことです。
下手くそな人間は魅力的ですよ。
いまは上手に生きようとする人間、要領のいい人間があまりに多い。
『いまこそ、感性は力』致知出版社
https://amzn.to/3wAopSC
「気に入らぬ 風もあろうに 柳かな」
という江戸時代の臨済宗の僧侶、仙崖(せんがい)和尚の歌がある。
世の中には理不尽なことが多くある。
批判や、揶揄(やゆ)、嘲笑という風。
ときには大風が吹くときもある。
気に入らぬことも多いが、柳に風と受け流す。
受け流すことができる人は…
「素朴愚拙」の人だ。
また、「素朴愚拙」の人は、「深沈厚重(しんちんこうじゅう)」の人でもある。
中国明代の儒学者である呂新吾(ろしんご)が 名著『呻吟語』で「人物」について語っている。
深沈厚重(しんちんこうじゅう) 是第一等素質
磊落豪遊(らいらくごうゆう) 是第二等素質
聡明才弁(そうめいさいべん) 是第三等素質
第一等の人物は、深沈厚重の人で、どっしりと落ち着いて深みのある人物。
細事にこだわらない豪放な人物は第二等。
頭が切れて弁の立つ人物は第三等である。
「深沈厚重」であり…
「素朴愚拙」の人を目指したい。
■メルマガの登録と解除はこちらから
http://hitonokokoro.com/
■「人の心に灯をともす」のfacebookページです♪
http://www.facebook.com/hitonokokoro
■【人の心に灯をともす】のブログはこちら
http://ameblo.jp/hiroo117/
■Twitterはこちらから
https://twitter.com/hiroo117
シェアさせて頂きました。
押忍
2023年2月9日木曜日
https://www.tbs.co.jp/taiikukaitv/
東京城西世田谷東支部に所属している長嶋一茂さんにTBSテレビ「炎の大会TV」が密着取材をしており、昨年開催された「2022国際親善大会」の試合の模様が2月11日(土)に放送されます。
皆様、是非ご覧ください!
番組名:炎の体育会TVスペシャル
放送予定日:2月11日(土)夜19:00~(関東地区18:51~ )
放送局:TBS系列
東京城西世田谷東支部に所属している長嶋一茂さんにTBSテレビ「炎の大会TV」が密着取材をしており、昨年開催された「2022国際親善大会」の試合の模様が2月11日(土)に放送されます。
皆様、是非ご覧ください!
番組名:炎の体育会TVスペシャル
放送予定日:2月11日(土)夜19:00~(関東地区18:51~ )
放送局:TBS系列
2023年2月8日水曜日
2023年2月7日火曜日
2023年2月6日月曜日
2023年2月5日日曜日
普通が一番
2023・2・5・日曜日
支部冬合宿全日程、無事に終了致しました。
極真合宿で学ぶことは当然、「極真空手の習得」この一字に集約される訳ですが、、
実はそれ以上に、「何一つ、自分の思い通りにならない」という事を学ぶ場であると、私は思うのです。
家に居ればお父さんお母さんが全て何でもやってくれます。
しかし、合宿では、全て自分の事は自分でやらなければなりません。
そして分単位での団体行動
たとえ、団体行動が苦手でもそんな事は許されません。
まさに理不尽さを敢えて学ぶ場なのです。
では、なぜ、敢えて型にはめるような合宿を行うのか、、
答えは簡単です。
「普通が一番であるという事に気づく(悟る)ため」であるのです。
そう、何事もなく、普通に生活出来ている事が、
実は奇跡であり、感謝に値する、という事に「気づく」ための合宿だと思うのです。
それにさえ気づく事が出来れば、敢えて浮世離れした修行なんてする必要などないのだと私は思います。
押忍
#冬合宿
#極真空手
支部冬合宿全日程、無事に終了致しました。
極真合宿で学ぶことは当然、「極真空手の習得」この一字に集約される訳ですが、、
実はそれ以上に、「何一つ、自分の思い通りにならない」という事を学ぶ場であると、私は思うのです。
家に居ればお父さんお母さんが全て何でもやってくれます。
しかし、合宿では、全て自分の事は自分でやらなければなりません。
そして分単位での団体行動
たとえ、団体行動が苦手でもそんな事は許されません。
まさに理不尽さを敢えて学ぶ場なのです。
では、なぜ、敢えて型にはめるような合宿を行うのか、、
答えは簡単です。
「普通が一番であるという事に気づく(悟る)ため」であるのです。
そう、何事もなく、普通に生活出来ている事が、
実は奇跡であり、感謝に値する、という事に「気づく」ための合宿だと思うのです。
それにさえ気づく事が出来れば、敢えて浮世離れした修行なんてする必要などないのだと私は思います。
押忍
#冬合宿
#極真空手
登録:
コメント (Atom)